
基礎生物学研究所

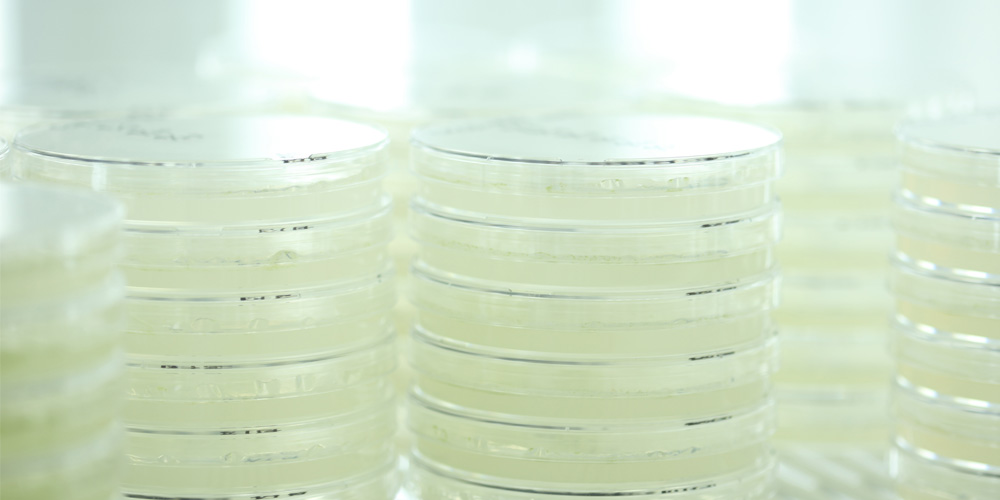


2017.10.06
京都大学
近畿大学
神戸大学
国立遺伝学研究所
基礎生物学研究所
東北大学
概要
河内孝之 生命科学研究科教授らの研究グループは、豪・モナシュ大学(ジョン L. ボウマン教授)、近畿大学(大和勝幸教授)、神戸大学(石崎公庸准教授)、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所(中村保一教授)、基礎生物学研究所(上田貴志教授)、東北大学(経塚淳子教授)をはじめとする国内外39の大学・研究機関と共同で、ゼニゴケの全ゲノム構造を解明しました。
イネやアブラナなどの被子植物からコケ植物まで、全ての陸上植物は藻類から進化し、約5億年前に水中から陸上へと進出しました。コケ植物の一種である苔類は、陸上進出後の最も早い時期に他の種から分かれて独自に進化した植物の系統の1つであり、陸上植物の祖先の特徴を保っています。このことから、苔類を用いた研究により、全ての陸上植物に共通する重要な分子メカニズムとその進化を解明することが可能になると期待されます。ゼニゴケは苔類の代表的な種の1つであり、15世紀以来、個体発生・生理・遺伝の様式について詳細な観察が行われてきました。近年、ゲノム編集技術[1]をはじめとする様々な遺伝子機能解析の手法が確立され、分子メカニズムの研究が容易な植物として改めて注目されるようになりました。
今回の研究でゼニゴケの全ゲノムの塩基配列が判明し、構造が明らかになりました。その結果、ゼニゴケは他の植物種に比べて、植物の発生過程・生理機能の制御に関わる遺伝子の重複[2]が非常に少ないこと、ゼニゴケが陸上植物の基本的な分子メカニズムの祖先型を持つことなどがわかりました。本研究により、ゼニゴケは、植物の基本的な分子メカニズムを研究するための新たな「モデル植物」として確立され、今後の研究により新しい育種技術などへの応用につながることが期待されます。
本研究成果は10月5日、Cellオンライン版に掲載されます。

1.背景
植物は、衣・食・住をはじめとして、私たちの日々の生活のあらゆる面に深く関わっています。植物の生理や発生の分子メカニズムをよりよく理解し利用するために、これまでイネや、アブラナ科シロイヌナズナなどの「モデル植物」が広く研究されてきました。これらの被子植物は実用性が高い一方で、遺伝子の重複が多く機能解析が困難であるなどの理由から、多くの基本的な分子メカニズムが未解明のままとなっています。
全ての陸上植物は、共通の祖先である藻類の一種から進化し、約5億年前に水中から陸上へと進出しました。この進出により、地球の環境そのものも変わっていったことが知られています。コケ植物の一種である苔類は、陸上進出後の最も早い時期に他の種から分かれて独自に進化した植物の系統の1つであり、単純な体の構造や、配偶体世代が生活環の大半を占める[3]など、初期の陸上植物の特徴を保っています。苔類は全ての陸上植物に共通する基本的な分子メカニズムを持つことが予想されるため、その解明によって植物の生理・発生の原理と、植物の多様な種が生み出された進化のメカニズムを統一的に理解することが可能になると期待されます。
ゼニゴケは苔類の代表的な種の1つであり、500年に渡る詳細な観察を通して個体の発生様式・生理反応・遺伝様式などが詳しく明らかにされてきました。また、近年では分子メカニズムの研究が容易な植物としても改めて注目されています。これらのことから近年、全世界的にゼニゴケの全ゲノム構造の解明が期待されていました。
2.研究手法・成果
今回の研究では、次世代シークエンス解析[4]と分子系統解析[5]によりゼニゴケの全ゲノム構造を解明しました。また、遺伝子の構成と他の植物種との系統関係も明らかにしました。
その結果、ゼニゴケ・ゲノムには約2万個の遺伝子が含まれており、陸上植物の祖先種と考えられる藻類に比べて遺伝子の数や種類が大きく増加していることがわかりました。また、雌雄異株であるゼニゴケの性を決めるX・Y染色体双方の構造も特定しました。特にX染色体に関しては今回、植物で初めてその構造が明らかにされました。今後の研究を通して、実際に植物の性を決めている遺伝子を明らかにできると期待されます。
ゼニゴケでは、様々な発生過程・生理応答を制御する「スイッチ」の役割を果たす転写因子[6]の遺伝子の数が他の植物種に比べて少ないという特徴がありました。しかし、陸上植物に共通する転写因子の基本セットは保持しており、遺伝子数の少なさは重複がほとんどないことによることがわかりました。このことから、約5億年前に植物が陸上化した段階で、陸上植物の基本遺伝子セットが確立しており、その後の他の植物種の祖先における多様化に伴って転写因子が重複したことが、その後の進化をもたらした要因の1つであると考えられます。
被子植物では、「植物ホルモン」と呼ばれる小さな化合物が生合成されて細胞内外の情報伝達に関わり、様々な発生過程・生理応答に重要な役割を果たしています。しかし、ゼニゴケは一部の植物ホルモンの生合成やシグナル情報伝達に必要な遺伝子をいくつかを持っていませんでした。この結果はゼニゴケのメカニズムが祖先型であり、進化の過程で細胞内外の情報伝達メカニズムを獲得したことを示唆しています。
植物が陸上で生きていくためには、紫外線などの光、乾燥、微生物や動物がもたらす病害に対する防御が必要です。ゼニゴケは、他の陸上植物にも見られる光受容体[7]を全て持っていました。また藻類には見られない、フラボノイドなど紫外線を防ぐ化合物の生合成に関わる遺伝子を獲得しており、これらは陸上植物の祖先種が土壌中の微生物から獲得した遺伝子だと考えられます。
被子植物では樹木などに見られるように、二次細胞壁と呼ばれる構造を作ります。これは細胞をより強固にする一方、水を通す組織としての役割も果たします。二次細胞壁の主な成分の1つであるリグニンと呼ばれる化合物の生合成には多くの遺伝子が必要ですが、ゼニゴケにはその一部のみが存在しており、類似の化合物が「リグニンの祖先型」として生合成され、役割を果たしていると考えられます。
ゼニゴケには病原菌に対し感知・応答するための遺伝子の数が少ないため、被子植物に見られるような遺伝子による病害防御システムは後の進化の過程で獲得したと考えられます。一方で、ゼニゴケは、テルペンと呼ばれる化合物を蓄積する特有の組織を持ち、食害に対する防御を行っています。テルペンの生合成に関わる遺伝子の多くも微生物から獲得したと考えられます。
3.波及効果、今後の予定
本成果で得られたゲノムの知見から、ゼニゴケは、全ての陸上植物が持つ基本的な分子メカニズムを祖先的な形で備えていることがわかりました。今後は、ゲノム編集技術などを駆使して個々の遺伝子の機能を明らかにするとともに、様々な解析をゲノム全体で網羅的に行う予定です。こうしたゼニゴケを新たな「モデル植物」とする研究により、未だ解明されていない全ての陸上植物に共通する重要な分子メカニズムを進化学的な観点から明らかにすることができ、さらに、農作物・有用植物への応用につながることが期待されます。
4.研究プロジェクトについて
本研究は科学研究費補助金 新学術領域研究「植物発生ロジックの多元的開拓」、新学術領域研究「先進ゲノム支援」、基盤研究(B)「陸上植物における光環境依存的な成長相転換機構の普遍性と多様性」等の支援を受けました。
[1] DNA切断酵素を用いてゲノムを自在に改変する技術。近年注目されているCRISPR/Cas9と呼ばれるシステムでは、微生物由来のCas9ヌクレアーゼを、ガイドRNAという分子でゲノムの特定の箇所に導き、塩基配列を自在に改変できる。
[2] 類似の遺伝子をゲノム中に複数持つこと。重複した遺伝子は類似の機能を持つことが多い。1つの遺伝子が働かないようにしてその機能を調べようとしても、別の重複した遺伝子がその効果を打ち消してしまい、結果として解析が困難になることがある。
[3] 陸上植物は、1セットのみゲノムをもつ「配偶体」と呼ばれる世代(発生段階)と、両親から受け継いだ2セットのゲノムを持つ「胞子体」と呼ばれる世代を交互に繰り返す。被子植物は、根・茎・葉をもつ状態が胞子体世代であり、減数分裂後に胚のうや花粉という配偶体世代を経て受精し、種子の中で胚を作り、再び胞子体となる。一方、コケ植物は、通常目にする植物体が配偶体世代であり、その中で卵や精子を形成し、受精後の短い期間のみ胞子体組織を作る。
[4] 短いDNA断片を大量かつ同時に解析する手法。短時間で全体のゲノムDNAや網羅的な遺伝子発現状態の解析が可能。
[5] タンパク質のアミノ酸配列や遺伝子の塩基配列どうしの類似性を計算し、分子の系統樹を明らかにする解析手法。
[6] 遺伝子の本体であるDNAからRNAへの「転写」を促進・抑制することで遺伝子の機能発現を調節するタンパク質。
[7] 光を刺激として受容することのできるタンパク質。植物は遠赤色−赤色光、青色光、紫外光の受容体を持つ。
<論文タイトルと著者>
タイトル:Insights into land plant evolution garnered from the Marchantia polymorpha genome
著者:John L. Bowman, Takayuki Kohchi, Katsuyuki T. Yamato, et al.
著者所属:京都大学、近畿大学、神戸大学、国立遺伝学研究所、奈良先端科学技術大学院大学、東京大学、名古屋大学、岡山大学、基礎生物学研究所、東北大学、東京農業大学、かずさDNA研究所、理化学研究所、首都大学東京、熊本大学、埼玉大学、豪・モナシュ大学、米・エネルギー省Joint Genome Institute、オーストリア・グレゴールメンデル研究所、独・オスナブルック大学、墨・INBIOTECA、英・ケンブリッジ大学、墨・CINVESTAV-IPN、英・オックスフォード大学、新・The New Zealand Institute for Plant & Food Research、スウェーデン・ウプサラ大学、オーストリア・ウィーンバイオテクノロジーセンター、仏・モンペリエ大学、スイス・チューリッヒ大学、米・ケンタッキー大学、国立台湾大学、米・コールドスプリングハーバー研究所、西・Centro Nacional de Biotecnologia-CSIC、米・アリゾナ大学、米・ミネソタ大学、独・マックスプランク研究所、独・ウルム大学掲載誌:Cell
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(17)31124-8
<お問い合わせ先>
河内孝之 生命科学研究科教授
TEL: 075-753-6389 (研究室)、FAX : 075-753-6127
E-mail: tkohchi@lif.kyoto-u.ac.jp