
基礎生物学研究所

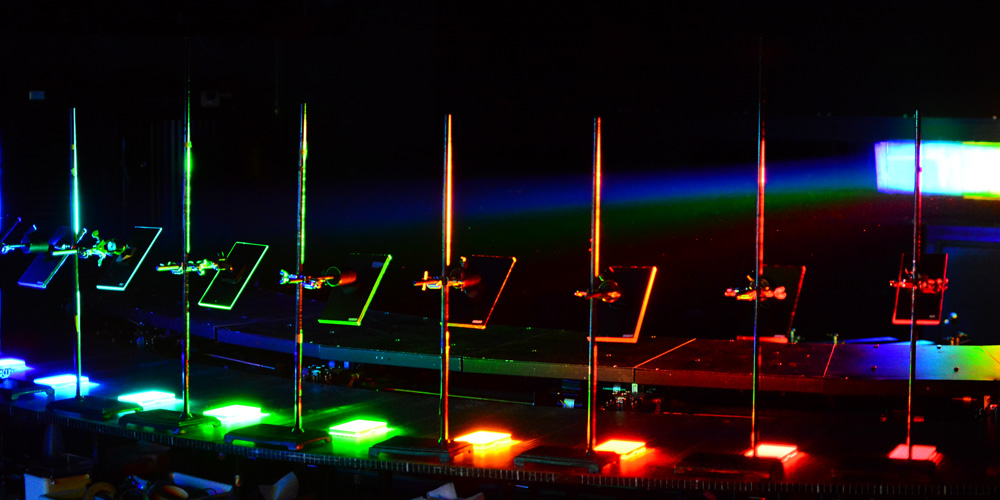


石 東博 (基礎生物学研究所 初期発生研究部門 / 京都大学大学院)
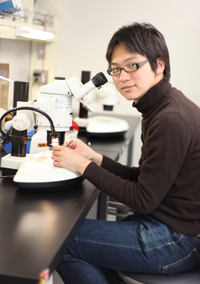 ショウジョウバエを研究していた教授がふと、マウスもちょっと調べてみたいなと。それが私が基生研にやってくるきっかけでした。恥ずかしながら、まだ当時は愛知と言えば名古屋ぐらいしか知らず、「キセイケン?ドコソコ?」状態でしたが、それが今となってはこの研究所にいることを誇りに思い、こうして筆を執ることになりました。他の大学院に所属したまま基生研で研究する大学院生は、特別共同利用研究員として受け入れられます。少し仰々しい名称ですが、実際の生活は普通の総研大の大学院生とほぼ同じです。リサーチアシスタントとして採用され経済的な援助を受けることもでき、基生研の懐の深さがうかがえます。一般の大学院と比べると、学生 が占める割合は少なく、いろんな方に名前を覚えてもらえ、サポートしていただきながら研究を進めることができます。今となっては7割以上の教員が私の名前を覚えているはず! 基生研には、研究所全体で学生を大切にして育てようという気風が感じられます。各研究室内に学生は2−3人しかいないのですが、ラボの枠を超えた学生同士の交流が盛んです。今年誕生したソフトボール部など、生理研・分子研の人とも知り合えるサークル活動も充実しています。人との出会いは人生の糧といいますが、そういう意味で、特別共同利用研究員として過ごした日々は実に豊作でありました。また、所属の大学院と基生研と両方の環境を体験することで、様々なことに気づき、学ぶことができました。この制度を多くの人に知ってもらい、基生研で素敵な研究生活と青春の日々を過ごしていただきたいと思います。(2011年記)
ショウジョウバエを研究していた教授がふと、マウスもちょっと調べてみたいなと。それが私が基生研にやってくるきっかけでした。恥ずかしながら、まだ当時は愛知と言えば名古屋ぐらいしか知らず、「キセイケン?ドコソコ?」状態でしたが、それが今となってはこの研究所にいることを誇りに思い、こうして筆を執ることになりました。他の大学院に所属したまま基生研で研究する大学院生は、特別共同利用研究員として受け入れられます。少し仰々しい名称ですが、実際の生活は普通の総研大の大学院生とほぼ同じです。リサーチアシスタントとして採用され経済的な援助を受けることもでき、基生研の懐の深さがうかがえます。一般の大学院と比べると、学生 が占める割合は少なく、いろんな方に名前を覚えてもらえ、サポートしていただきながら研究を進めることができます。今となっては7割以上の教員が私の名前を覚えているはず! 基生研には、研究所全体で学生を大切にして育てようという気風が感じられます。各研究室内に学生は2−3人しかいないのですが、ラボの枠を超えた学生同士の交流が盛んです。今年誕生したソフトボール部など、生理研・分子研の人とも知り合えるサークル活動も充実しています。人との出会いは人生の糧といいますが、そういう意味で、特別共同利用研究員として過ごした日々は実に豊作でありました。また、所属の大学院と基生研と両方の環境を体験することで、様々なことに気づき、学ぶことができました。この制度を多くの人に知ってもらい、基生研で素敵な研究生活と青春の日々を過ごしていただきたいと思います。(2011年記)
為重 才覚 (基礎生物学研究所 植物器官形成学研究部門 / 京都大学大学院)
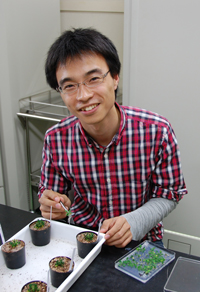 私は特別共同利用研究員制度を利用して、京大の大学院生として基礎生物学研究所で研究を行っています。複数のラボに所属する身というのは、複雑で大変そうに聞こえるかもしれませんが、実際は大きなメリットがあります。簡単に言うと、すべて2倍になります。指導してくれる人、研究に使える設備、さまざまな研究者と接する機会、学生仲間、2倍になると嬉しいものがたくさんあります。私の場合京大のボスも基生研でのボスも懐が深く、暖かく応援・指導してくれるというのがもちろん最大のメリットですが。学生仲間も私にとってかなり重要です。 基生研では総研大生も他の所属の学生もあまり垣根がなく、他のラボの学生とワイワイ遊んだり飲んだりする機会もあるし、(単位は出ませんが)出たい授業には自由に出られるし、お互い研究の相談なども気軽にしています。ちなみに私の場合は一時期、勝手に卓球部長を自称して他のラボの人達と卓球をしていました。ただ、飽きっぽい性格のため卓球部は自然消滅してしまいましたが、最近は誘われて何人かでボルダリングに行ったりしています。もちろん学生以外の他のラボの人達との交流も実り多いものです。基生研では他のラボの先生や有志が主催する勉強会、セミナーがいくつもあるからです。さすが基生研で研究をしている方々だけに、さまざまな観察技術、解析手法に精通したスペシャリストが揃っていて、そんな人達が参加する勉強会に出席していると、自分の無学さを感じるのは言うまでもありません。でも自分の方から積極的に参加して質問するくせさえつければ、どんどん自分の知識や人脈を広げることができます。実際そうして身につけた顕微鏡のノウハウや統計手法は私自身の研究に役立っていますし、そうして知り合った方々に研究の相談に乗ってもらったり、一緒に遊んだ りと、基生研生活を満喫しています。基生研での環境を活用できるかどうかはもちろん本人次第だと思いますが、特別共同利用研究員は多くの大学院生にとって魅力的な学生生活の選択肢だと思います。(2012年記)
私は特別共同利用研究員制度を利用して、京大の大学院生として基礎生物学研究所で研究を行っています。複数のラボに所属する身というのは、複雑で大変そうに聞こえるかもしれませんが、実際は大きなメリットがあります。簡単に言うと、すべて2倍になります。指導してくれる人、研究に使える設備、さまざまな研究者と接する機会、学生仲間、2倍になると嬉しいものがたくさんあります。私の場合京大のボスも基生研でのボスも懐が深く、暖かく応援・指導してくれるというのがもちろん最大のメリットですが。学生仲間も私にとってかなり重要です。 基生研では総研大生も他の所属の学生もあまり垣根がなく、他のラボの学生とワイワイ遊んだり飲んだりする機会もあるし、(単位は出ませんが)出たい授業には自由に出られるし、お互い研究の相談なども気軽にしています。ちなみに私の場合は一時期、勝手に卓球部長を自称して他のラボの人達と卓球をしていました。ただ、飽きっぽい性格のため卓球部は自然消滅してしまいましたが、最近は誘われて何人かでボルダリングに行ったりしています。もちろん学生以外の他のラボの人達との交流も実り多いものです。基生研では他のラボの先生や有志が主催する勉強会、セミナーがいくつもあるからです。さすが基生研で研究をしている方々だけに、さまざまな観察技術、解析手法に精通したスペシャリストが揃っていて、そんな人達が参加する勉強会に出席していると、自分の無学さを感じるのは言うまでもありません。でも自分の方から積極的に参加して質問するくせさえつければ、どんどん自分の知識や人脈を広げることができます。実際そうして身につけた顕微鏡のノウハウや統計手法は私自身の研究に役立っていますし、そうして知り合った方々に研究の相談に乗ってもらったり、一緒に遊んだ りと、基生研生活を満喫しています。基生研での環境を活用できるかどうかはもちろん本人次第だと思いますが、特別共同利用研究員は多くの大学院生にとって魅力的な学生生活の選択肢だと思います。(2012年記)