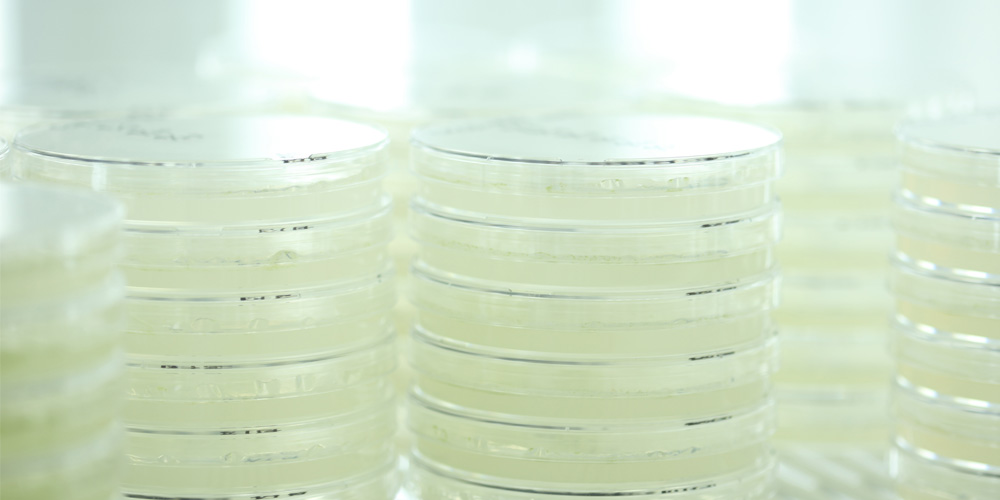勝木元也先生(基礎生物学研究所名誉教授)が12月3日にご逝去されました。
勝木元也先生は、1998年4月から2001年3月末まで細胞増殖研究部門 客員教授(本務:東京大学医科学研究所附属ヒト疾患モデル研究センター教授)を、2001年4月から2007年3月末まで基礎生物学研究所第6代所長を務められました。また、2004年4月から2012年3月末まで自然科学研究機構の理事を務められました。
『巨星逝く 〜人を動かす達人 勝木元也(基礎生物学研究所・元所長 自然科学研究機構・元理事) を偲ぶ〜』
新潟大学脳研究所 動物資源開発研究分野
笹岡俊邦
私は、2003年8月から2011年3月まで基礎生物学研究所でお世話になりました。私の体験からの勝木元也先生の姿を書かせていただきます。誌面の都合で、一部の先生方のお名前のみを書かせていただいていることをご了解願います。
勝木先生は、日本のトランスジェニックマウス時代の隆盛に大活躍された一人です。1980年代半ばに、まず、企図振戦という激しく震える「シバラー」という神経系の変異マウスの欠損遺伝子の研究に取り組まれました。木村穰先生(現:東海大学 教授)が、シバラー欠損遺伝子がミエリン塩基性タンパク質(MBP)遺伝子であることを見出されていて、勝木先生は、そのMBP遺伝子のシバラーマウスへの導入による、企図振戦の回復の研究を、木村先生、そして胚移植の達人の横山峯介先生(前:新潟大 教授、現:実中研 研究員)の3人を中心にして取り組まれ、見事成功されました。併せて、MBP遺伝子発現の抑制をアンチセンスRNAの導入により誘導するトランスジェニックマウスを作製し、企図振戦を引き起こす実証実験にも大成功され、世界に大きなインパクトを与えられました(Katsuki
et al., Science 1988, Kimura
et al., PNAS 1989)。
さらに、勝木先生らは、ヒトのc-H-
rasがん遺伝子を、正常のゲノム構造のまま導入したrasH2トランスジェニックマウスを作製し、発がん実験を行ったところ、マウスに見られたがん組織では、ヒトH-
ras遺伝子のみに、ヒトのがん組織と同じ突然変異が生じることを発見されました(Saitoh
et al. Oncogene 1990)。このrasH2マウスは、発がん研究に世界中で使われるとともに、医薬品の発がん性試験用として実用化され、現在では、米国でも発がん性試験用の標準動物として主流になっています (
https://www.ciea.or.jp/laboratory_animal/rash2_mouse.html)。
1989年当時、私は名古屋大学の大学院生であり、岡崎で開催された勝木先生の講演で、マウス発生工学実験によるトランスジェニックマウスの研究に魅せられてしまい、当時大学院生の小林和人さん(現:福島医大 教授)と一緒に、実験動物中央研究所(現:実中研)での訓練を受け入れてもらいました。
『求む隊員
至難の旅。僅かな報酬。極寒。暗黒の長い日々。絶えざる危険。生還の保証無し。
成功の暁には名誉と賞賛を得る。
アーネスト・シャクルトン』
これは、英国のアーネスト・シャックルトンが、1914年に新聞に掲載した南極探検隊員の求人広告内容で、5,000人余りの応募者があったことが有名です。実中研の勝木先生が主宰する発生工学研究室に初めて伺った時、この広告が、入り口に掲げられていることに、凄いところだと、とても驚きました。
小林さんと私は、勝木先生、横山峯介先生、木村穰先生、長谷川孝徳さん(現:千葉大)、高橋利一さん(現:実中研 センター長)、そして、勝木先生の奥様の邦子様からも、マウス発生工学実験について、丁寧で詳細な指導をいただきました。
勝木研究室は、国内外との多くの共同研究に併せて、全国から数多くの方を受け入れ、マウス発生工学実験の訓練をされていました。丁度、饗場篤さん(現:東京大 教授)も来られて、一緒に学びました。毎日のように朝から深夜まで、トランスジェニックマウスの実験が行われていて、実験技術については、「100回試して1回成功すれば、成功したと思うのはアマチュアで、99回成功しても1回失敗すれば、失敗というのがプロだ!」との指導のもと、常々100%の結果となることに皆さんが徹していて、科学に対する、真摯で厳しい姿勢を訓練するところでした。私も迫力のある指導を何度も受けました。
そして、丁度、ES細胞によるノックアウトマウス作製の世界初の成功が発表されたおり、勝木先生から誘われて、私は、実中研でノックアウトマウスの実験システムの立ち上げに、中村健司さん(現:新渡戸文化短大 教授)、中尾和貴さん(現:大阪大 教授)と一緒に取り組みました。当初は、さまざまな困難があり、まさに「至難の旅」でした。
その後、1992年に勝木先生が九州大学生体防御医学研究所に異動の折、私は助手に採用していただきました。九大生医研では、権藤洋一先生(現:東海大 教授)、中村健司さん、中尾和貴さん、邦子様をはじめとして、発生工学実験システムを立ち上げられ、さらに饗場篤さんが、米国MITの利根川進研究室から着任されて、膨大な数の遺伝子改変マウスの作製と解析の研究を進められました。私は、この時期に米国留学の機会をいただくことができました。
1996年に、勝木先生は、東大医科研にご異動になり、マウス発生工学実験システムをさらに大規模に展開され、併せて医科研の動物実験施設を大改修されました。
この頃、勝木先生は、ご自身の生い立ちから、基生研 所長就任の頃までの道のりについて、2003年のJT生命誌39号の「日本の科学の未来を創る-発生工学の始まり」(
https://brh.co.jp/s_library/interview/39/)のインタビューにて、いきいきと語られています。
基生研では、遺伝子改変生物の研究のために、1998年に野田昌晴先生(現:東京科学大 特任教授)をはじめとした先生方のご尽力で、形質転換生物研究施設が新設されました。2001年に、勝木先生は基生研所長に就任され、実験動物のSPF飼育環境の整備にも尽力されました。当時、明大寺地区のプレハブ造りの建物でマウス発生工学実験が行われていて、当該施設の運営は、渡辺英治さん、江藤智生さん(現:実中研 室長)、宮川敦士さん(現:東大医科研 技術職員)、野口裕司さん(現:基生研 技術職員)、邦子様が中心になって奮闘されていました。
2003年に山手地区に形質転換生物研究施設の動物実験施設が完成し、施設の担当教員として、田中実さん(現:名古屋大 教授)と私が採用されました。そこで、渡辺英治さんが明大寺地区のマウス施設の担当、田中実さんが山手地区のメダカ施設の担当、私が山手地区のマウス施設の担当となり、林晃司さん(現:基生研 技術職員)、野口さん、吉田悦子さん((株)ジェーエーシー)を中心に、立ち上げに頑張りました。
勝木先生と邦子様は、動物実験施設の稼働にあたり、横山峯介先生、並びにこれまで共に仕事をされた、ノウハウを持つプロの方々を次々と招かれ、私たちは卓越した仕事を教わりました。
勝木先生は、神仏への信心が深く、以前から実験の成功のために祈願され、祈祷の御札を研究室に掲げられていました。時に、御札が床に落ちていることがあり、皆が驚いて元に戻していました。
勝木先生は、実験で実証する科学をされているところ、信心の深いことを私は不思議に思っていましたが、山手地区への引越しの折には、勝木先生と邦子様は安全祈願のため、豊川稲荷にてご祈祷をされて動物実験施設の安全な稼働を見守ってくださいました。
また、2004年に、勝木先生は、要望の高かった明大寺地区のSPF動物飼育施設の整備のため、共通施設棟Ⅱの地下を改修し動物飼育施設が設置されて、渡辺英治さん、野口裕司さんと宮川敦士さんが、運営に尽力されました。
勝木先生は、若い人をとても大切にされ、当時総研大の大学院生であった、荒川聡子さん(現:東京科学大 教授)は、勝木先生と邦子様をはじめ、温かく丁寧な指導を受けられて、見事に論文を完成し、学位を取得されました。
大学院生の勧誘イベントとして始まった、基生研オープンキャンパス第1回(2008年8月29日)には、前日から記録的大雨で、未明に山手地区の全停電により動物実験施設の機能が全停止しました。真夜中の復旧作業に私たち教職員が対応したことはもちろんですが、事務センターのトップの方も動物実験施設に来られて驚きました。勝木先生が常に語る、緊急時対応の重要性を理解して、動いてくださったものと思います。なお、当日は、東京から学部学生さんがオープンキャンパスに参加してくれて、皆さんに大いに歓待されました。
ところが、動物実験施設の活動が軌道に乗り始めた頃、邦子様が体調を崩され、東京でご療養されることになり、勝木先生は、介護をなさりつつ岡崎と東京を通って所長を務められました。
勝木先生は、基生研所長退任後、自然科学研究機構理事を経て、日本学術振興会(JSPS)の学術システム研究センター副所長を務められ、科研費システム改革に取り組まれました。改革を議論する会議では関連する多くの方が意見を述べるように働きかけられ、改革を進められたと伺っています。
1年ほど前に横山峯介先生に伺ったところ、勝木先生はご自身の療養中にあって、JSPSの方々と、科研費システム改革の仕事を中心に「ふたたび、学問のススメ」のような内容の本を書いていらっしゃるとのことでした。そしてJSPSの責任者の方から、ちょうど2024年9月に、以下の本が出版されたことをお聞きしました。
「科研費システム改革と科研費獲得の真髄」勝木元也 幻冬舎 (2024/9/25)
(
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784344691575)
私も拝読したところ、科研費システム改革では、多くの人の意見を反映して大幅な改革を進めたこと、そして日本の科学の現在の課題と将来について、勝木先生の率直なご意見が述べられています。
勝木先生と邦子様は、天国でも、きっと、これまでのように多くの人に働きかけをなさって、動かしていらっしゃることと思います。
お二人が残された温かい思いと行動力は、私たちの心の中に生き続け、これからも道しるべとなることでしょう。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

勝木元也先生と邦子様
(撮影:大西成明)