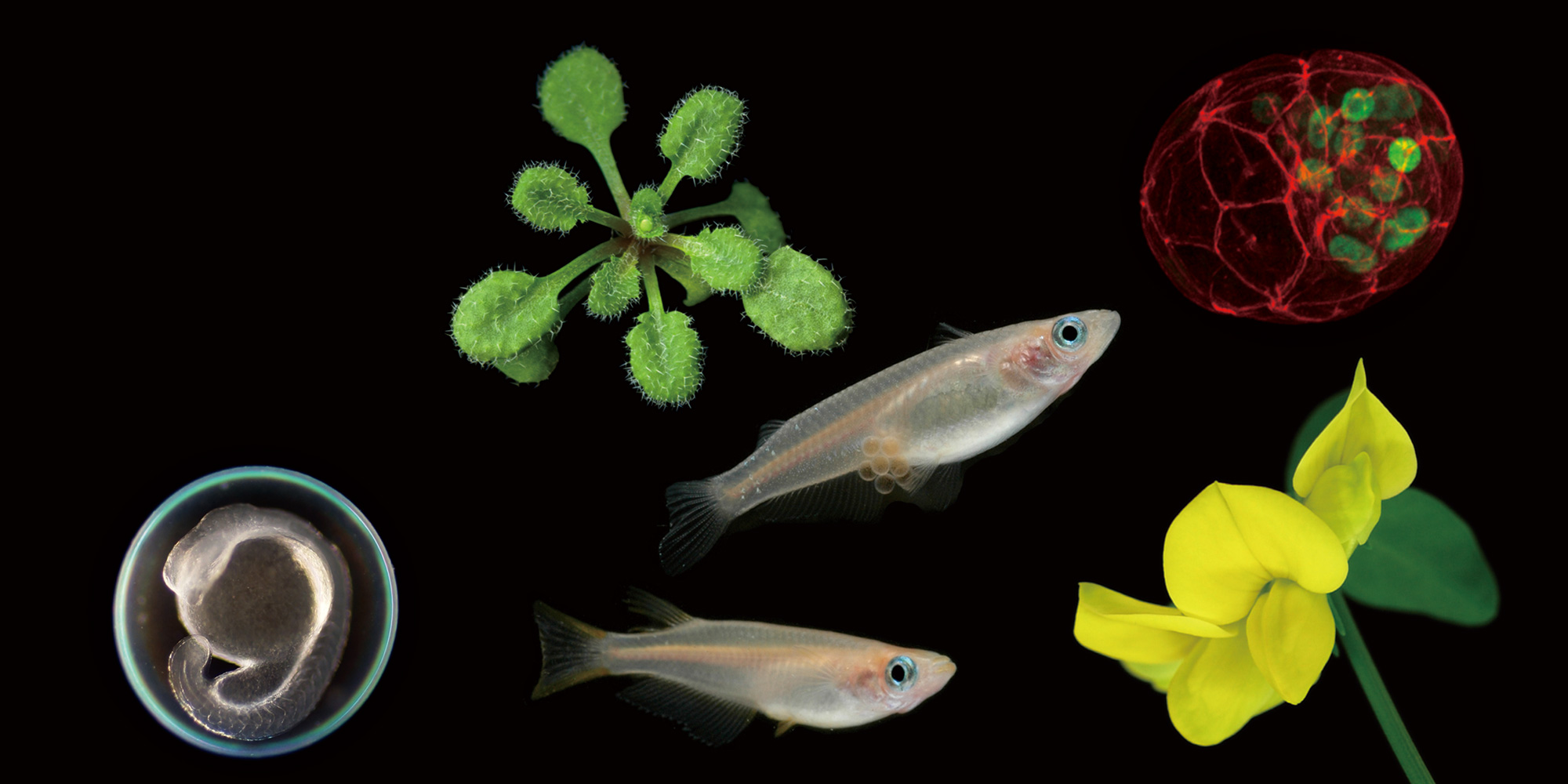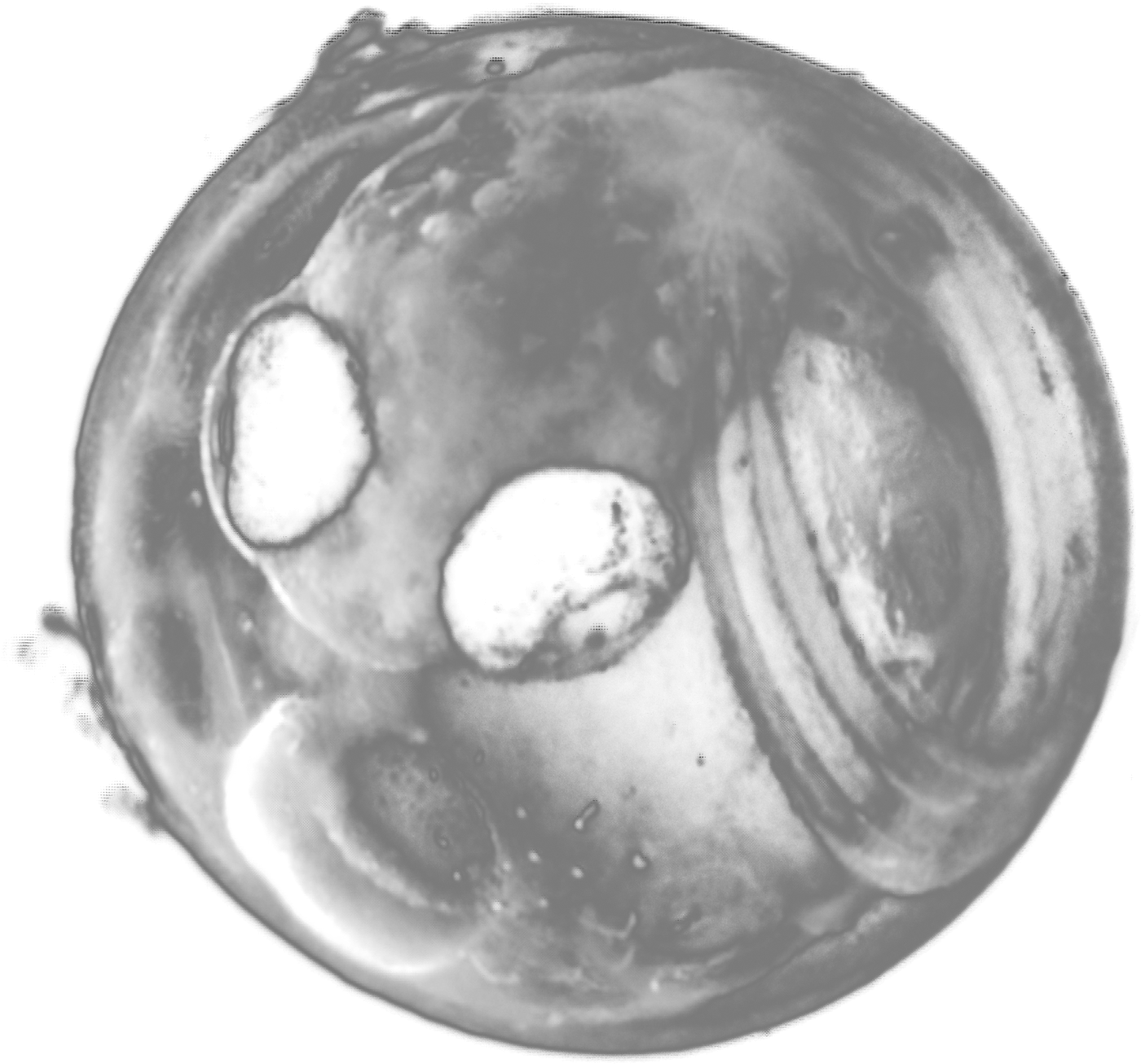2003.10.24 部門公開セミナー
におい知覚のメカニズム:システムレベルでの理解に向けて
内田直滋 (Cold Spring Harbor Laboratory)
2003年10月24日(金) 15:00 より 16:30 まで
明大寺地区1階会議室(111)2003-10-25
統合バイオサイエンスセンター 分子発生 高田慎治 内線5241
感覚系を研究する際、分子レベル、ニューロンレベルのはたらきを解析するのに加えて、その感覚系が、動物のどういう目的のために使われているか、つまり、システム、行動レベルでの目的、はたらきを考える視点を持つことが重要であろう。におい知覚は、離れた対象物から放たれる化学物質(の混合物)を認識することが第一の目的である。この際、(1)におい(化学物質)を合目的的に認識あるいは分類すること、(2)それが対象物との距離が変化した場合、つまり濃度が変化した場合でも正しく行われることが必要である。
嗅覚系には1000種類ものにおい受容体が存在し、におい感覚は化学物質(あるいはその混合物)が特異的な組み合わせの受容体を活性化することから始まる。脳は1000種類も存在するにおい受容体の活性化パターン(コード)をもとに上のふたつの要求を達成しなければならない。におい物質の濃度が変化すると活性化されるにおい受容体の組み合わせが変化するので、単純な「組み合わせ」を読むだけではふたつの要求は達成されない。本セミナーでは、どのような脳のメカニズムで上のふたつの要求が達成されるかを理解するために行ったふたつのアプローチを紹介する。
(1)古来、におい物質の構造と、感覚されるにおいの質の関係は謎であったが、光学的イメージングを用いた実験から、におい物質の化学構造に対応した地図(spatial representation)が嗅球(olfactory bulb)に存在することがわかった1。このにおい地図は、化学構造のパラメーター(官能基、炭素鎖の長さ)を階層的に表現しており、化学構造とにおいとの対応と相関が見られた。
(2)ラットにおいて、におい知覚を調べる精神物理学的行動実験のシステムを開発した2。この実験から、におい物質の「比」がにおい知覚の重要な決定因子であることが分かった。この実験は、動物がにおい物質の「比」を感知する能力を持っていることを示しており、脳の中にそのようなメカニズムが存在していることを示唆する。におい物質の「比」は濃度によって変化しない量であるので、上記の第二の目的を達成する上で重要な役割を果たすと考えられる。この結果は、上記の「におい地図」がどう読まれるか、を考える上で興味深い視点を与える。
現在、行動中のラットからテトロードを用いた電気生理を行っており、さらに分子生物学的、遺伝学的手法を組み合わせることにより、今回開発した行動実験系が、感覚系や認知機能を研究するモデルシステムになることが期待できる。
1. Uchida‚ N.‚ Takahashi‚ Y. K.‚ Tanifuji‚ M. & Mori‚ K. Odor maps in the mammalian olfactory bulb: domain organization and odorant stuctural features. Nat Neurosic 3‚ 1035-43(2000).
2. Uchida‚ N. & Mainen‚ Z. F. Speed and accuracy of olfactory discrimination in the rat. Nat Neurosic‚ In press(2003).