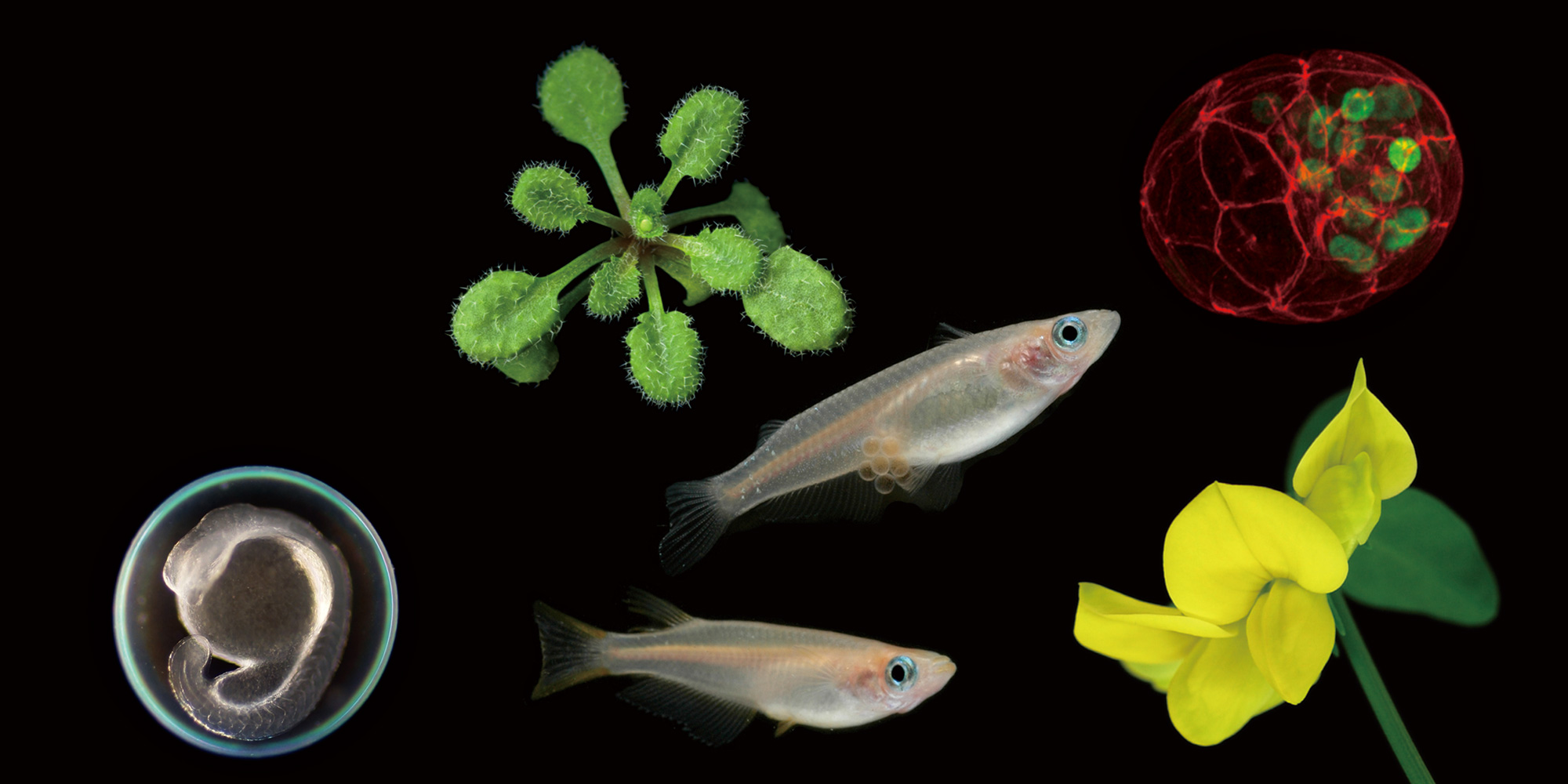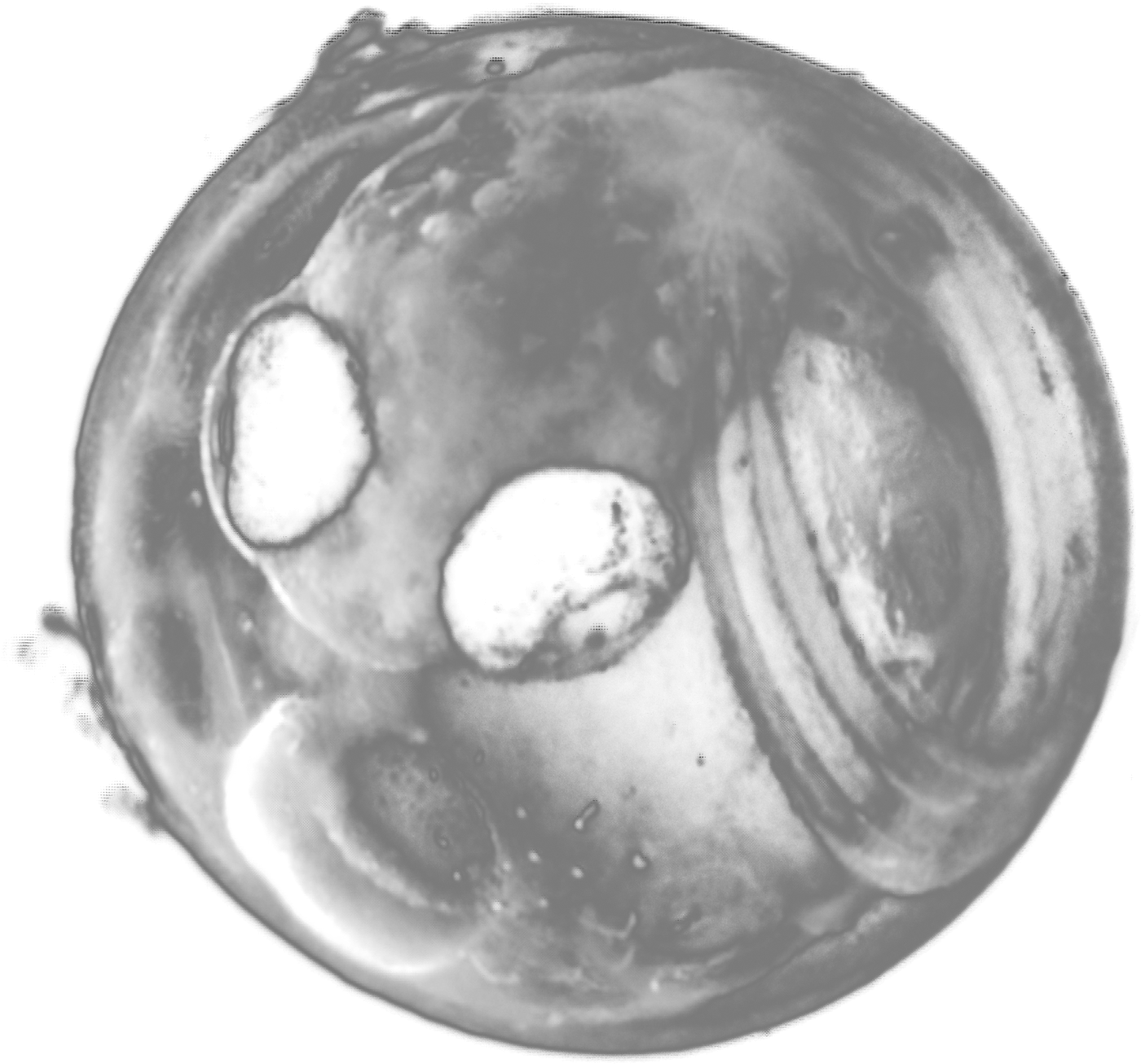2013.10.21 基生研セミナー
生命とは何か-散逸構造とノイズの観点から
長沼毅 (広島大学大学院生物圏科学研究科)
2013年10月21日(月) 16:00 より 17:30 まで
明大寺地区1階 会議室(111)
ゲノム情報 内山 郁夫 (7629)
高きから低きに流れる水は「重力的な位置エネルギー」を消費しながら「渦」をつくる。渦をつくる水分子は刻一刻と入れ替わるが、渦は維持される。 私たちも、体をつくる分子や原子は日々入れ替わりつつ、体は維持されている。それは「化学的な位置エネルギー」を消費しつつ維持されるので「生命の渦」と呼んでもいいだろう。
水の渦はいわゆる「散逸構造」である。生命もまた「渦」であるならば、生命は「自己複製する散逸構造」と考えることができる。しかし、生命は単なる散逸構造ではない。約40億年間ずっと維持されてきた“タフな渦”である。一方、散逸構造は撹乱に弱く、タフではない。このタフさをロバストネス(頑強さ)という。つまり、生命は「自己複製するロバストな渦」であると云えよう。
生命のロバストネスはどこから来るのだろう。ひとつには「冗長性」がある。たとえば代表的な放射線耐性菌Deinococcus radioduransは4コピーのゲノムを持つことで高いDNA修復能を有すると考えられている。私はもうひとつ「ノイズ」もまた生命のロバストネスに 寄与していると考える。ある刺激に対して生命は決まった応答をする、ある意味で“刺激-応答マシン”である。しかし、このマシンは時々“外れた” 応答をする。それはおそらく遺伝子発現などにおけるノイズのせいであろう。この発表では、生命現象におけるノイズの意義について考察を巡らせてみたい。