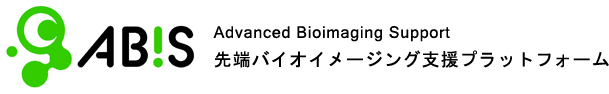成果発表
【画像解析支援:加藤輝(基礎生物学研究所)】[2025.05.21]
近藤寿人 顧問(生命誌研究館 前:京都産業大学 教授)の論文が Frontiers in Cell and Developmental Biology に掲載されました
Takami N., Kato K., Yoshihi K., Kawamura A., Iida H., Kondoh H. The potent neuroepithelium-promoting activity of Otx2 during gastrulation, as demonstrated by its exogenous epiblast-wide expression in chicken embryos. Frontiers in Cell and Developmental Biology (2025) DOI:10.3389/fcell.2025.1599287
<概要>Otx2は頭部形成に必須の転写因子ですが、神経系初期発生における制御機能は不明でした。ニワトリ胚を用いた本研究によって、Otx2にはエピブラストから神経系への発生を促進する活性があること、屈曲に抗する強靭な神経上皮を形成する活性があることが示されました。これらの活性によって、大きな神経組織としての脳が早期に発生します。ABiS・画像解析支援(支援担当:加藤輝)では、Otx2発現によって変化するエピブラスト細胞の移動を、ライブイメージングによって解析しました。
【電子顕微鏡支援担当:大野伸彦(生理学研究所)】[2025.04.05]
樽野陽幸 教授(京都府立医科大学)の論文が Cell に掲載されました
咳と嚥下のスイッチ 喉に新たな感覚器官を発見
~咳治療に道筋、喉ごし感覚の⼀端か~
Soma S., Hayatsu N., Nomura K., Sherwood M. W., Murakami T., Sugiyama Y., Suematsu N., Aoki T., Yamada Y., Asayama M., Kaneko M., Ohbayashi K., Arizono M., Ohtsuka M., Hamada S., Matsumoto I., Iwasaki Y., Ohno N., Okazaki Y., Taruno A. Channel synapse mediates neurotransmission of airway protective chemoreflexes. Cell (2025) DOI:10.1016/j.cell.2025.03.007
<概要>本研究では、マウスを用いた実験で、苦味のある毒素を含む植物抽出物、タバコの煙、空気汚染物質、病原体関連物質など多様な侵害化学物質に対して生じる咳や嚥下を担う喉の感覚細胞を新たに発見しました。さらに、これらの細胞がアレルギー性の咳過敏症に関与することを明らかにしました。本研究成果をもとに、今後、この咳の機序がヒトにも存在することが明らかになれば、慢性咳嗽の診断および治療法に新たな道筋を与えることが期待されます。ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:大野伸彦)では、SBF-SEMを用いた3D-CLEMによる解析支援を行いました。
 プレスリリース(JSTのサイト)
プレスリリース(JSTのサイト)
 プレスリリース(京都府立医科大学のサイト)
プレスリリース(京都府立医科大学のサイト)
 プレスリリース(理化学研究所のサイト)
プレスリリース(理化学研究所のサイト)
【電子顕微鏡支援:豊岡公徳(理化学研究所)】[2025.04.08]
坂本亘 教授(岡山大学)の論文が Plant Physiologyに掲載されました
生命の源、光合成の足場を保つしくみの解明~「足場=チラコイド膜」を守り植物を高温に強くする~
Gachie S. W., Muhire A., Li D., Kawamoto A., Takeda-Kamiya N., Goto Y., Sato M., Toyooka K., Yoshimura R., Takami T., Zhang L., Kurisu G., Terachi T., Sakamoto W. The thylakoid membrane remodeling protein VIPP1 forms bundled oligomers in tobacco chloroplasts. Plant Physiology (2025) DOI:10.1093/plphys/kiaf137
<概要>本研究では、光合成における光エネルギーの転換反応が生じる「チラコイド膜」の維持に、「VIPP1」と呼ばれるタンパク質が重要な役目を果たしていることを明らかにしました。ABiSの電子顕微鏡支援(支援担当:豊岡公徳)では、電子線トモグラフィー技術によるVIPP1の構造解析に関する支援を行いました。
 プレスリリース(岡山大学のサイト)
プレスリリース(岡山大学のサイト)
 プレスリリース(理化学研究所のサイト)
プレスリリース(理化学研究所のサイト)
 プレスリリース(京都産業大学のサイト)
プレスリリース(京都産業大学のサイト)
【光学顕微鏡支援:亀井保博(基礎生物学研究所)】[2025.02.27]
富樫英 研究員(神戸大学)の論文が Cell Reports に掲載されました
細胞の接着を支える新たな仕組みを解明 ~アファディンが液滴のように集まることで接着複合体を形成 ~
Kuno S., Nakamura R., Otani T., Togashi H. Multivalent afadin interaction promotes IDR-mediated condensate formation and junctional separation of epithelial cells. Cell Rep (2025) DOI:10.1016/j.celrep.2025.115335
<概要>本研究では、アファディンが接着分子や細胞骨格と多価相互作用することで、IDR依存的な凝集体を形成し、初期接着形成時に線状AJへの効率的な集積を促進することを明らかにしました。さらに、アファディンとZO-1が異なる凝集体を形成し、それぞれ異なる分布を示すことから、上皮細胞の接着複合体内でAJとTJの分離に関わるメカニズムが示唆されました。ABiSの光学顕微鏡支援(支援担当:亀井保博)では、細胞内分子濃度および拡散速度の定量的な解析に関する支援を行いました。
 プレスリリース(神戸大学のサイト)
プレスリリース(神戸大学のサイト)
【光学顕微鏡支援:東山哲也(名古屋大学 現:東京大学)・電子顕微鏡支援:渡辺雅彦(北海道大学)、深澤有吾(福井大学)】[2025.02.28]
上田(石原)奈津実 准教授(東邦大学)の論文が Cell Reports に掲載されました
長期記憶を定着させるタンパク質 ” セプチン3 ” の働きを解明 ~ 記憶の維持や回復を支える治療戦略への展開に期待 ~
Ageta-Ishihara N., Fukazawa Y., Arima-Yoshida F., Okuno H., Ishii Y., Takao K., Konno K., Fujishima K., Ageta H., Hioki H., Tsuchida K., Sato Y., Kengaku M., Watanabe M., Watabe A. M., Manabe T., Miyakawa T., Inokuchi K., Bito H., Kinoshita M. Septin 3 regulates memory and L-LTP-dependent extension of endoplasmic reticulum into spines. Cell Rep (2025) DOI:10.1016/j.celrep.2025.115352
<概要>本研究では、Septin 3がシナプス伝達の後期長期増強現象 (L-LTP) 依存的な小胞体の樹状突起スパイ
ンへの伸長を介してスパイン内カルシウムイオン濃度を制御することで、記憶形成を制御している
ことを発見しました。ABiSの電子顕微鏡支援(支援担当:渡辺雅彦・深澤有吾)では、免疫組織学的
解析に適した特異抗体の作製、電子顕微鏡を用いたSeptin 3のシナプス結合内局在とシナプス結合内
超微細構造の三次元再構築解析を支援し、光学顕微鏡支援(支援担当:東山哲也・佐藤良勝)では、小胞体の
ライブイメージング解析を支援しました。
 プレスリリース(名古屋大学のサイト)
プレスリリース(名古屋大学のサイト)
 プレスリリース(東邦大学のサイト)
プレスリリース(東邦大学のサイト)
【光学顕微鏡支援担当:青木一洋(京都大学)[2024.10.30]
井上実 医長(静岡がんセンター放射線治療科)の論文が PNASに掲載されました
Inoue M., Takayama K., Hashimoto R., Enomoto M., Date N., Ohsumi A., Mizowaki T. Hyponatremia unleashes neutrophil extracellular traps elevating life-threatening pulmonary embolism risk. Proc Natl Acad Sci U S A (2024) DOI:10.1073/pnas.2404947121
<概要>本研究では、マウスおよびヒトの好中球において細胞外ナトリウム濃度の低下により、非感染状態であってもNeutrophil extracellular traps (NETs)が誘導されることを発見しました。本機構により誘導されるNETsは、感染下で起こる肺塞栓の促進因子となりうることも併せて発見しました。ABiS・光学顕微鏡支援(支援担当:青木一洋)では、二光子励起顕微鏡を用いてマウス肺のライブイメージング支援を行いました。
【電子顕微鏡支援:豊岡公徳(理化学研究所)】[2025.02.04]
山田萌恵 助教(名古屋大学)の論文が Nature Plants に掲載されました
細胞板の形成を導く”分子モーター”を特定 植物の器官発生時の連続的な細胞分裂に必須の機構
<概要>本研究では、基部陸上植物ヒメツリガネゴケをモデルとして、細胞板形成過程を調べることにより、細胞板材料を含む小胞を輸送する分子モーター・キネシン12を同定しました。ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:豊岡公徳)では、細胞質分裂中のヒメツリガネゴケから細胞切片を作製し、細胞板形成部位を電子顕微鏡観察する支援を行いました。
【光学顕微鏡支援:稲葉一男(筑波大学)】[2024.11.27]
山本遼介 講師(大阪大学)の論文がmSphereに掲載されました
Yamamoto R., Tanaka Y., Orii S., Shiba K., Inaba K., Kon T. Chlamydomonas IC97, an intermediate chain of the flagellar dynein f/I1, is required for normal flagellar and cellular motility. mSphere (2024)DOI: 10.1128/msphere.00558-24
<概要>本研究では、単細胞緑藻クラミドモナスをモデル生物として用い、繊毛ダイニンのサブユニットに欠損を持つ変異株の繊毛運動を詳細に観察することで、当該サブユニットの欠損が繊毛運動に与える影響を明らかにしました。ABiS・光学顕微鏡支援(支援担当:稲葉一男・柴小菊)では、高速度カメラを用いてクラミドモナス変異株の繊毛運動を可視化する支援を行いました。
【光学顕微鏡支援:三上秀治(北海道大学)】[2024.12.27]
東恒仁 助教(北海道大学)の論文がJournal of Pharmacological Sciences に掲載されました
<概要>タバコ煙ガス相の細胞傷害因子である不飽和カルボニル化合物に対するマクロファージの感受性に関与する因子を分子レベルで調べることにより、シスチントランスポーターであるSLC7A11の発現量が不飽和カルボニル化合物感受性を決定する因子の一つであることを発見しました。ABiS・光学顕微鏡支援(支援担当:三上秀治)では、ワイドフィールド顕微鏡による細胞形態のイメージングの支援を行いました。
【電子顕微鏡支援担当:太田啓介(久留米大学)】[2024.12.13]
小柴琢己 教授(福岡大学)の論文が Journal of Biological Chemistryに掲載されました
Ban T., Kuroda K., Nishigori M., Yamashita K., Ohta K., Koshiba T. Prohibitin 1 tethers lipid membranes and regulates OPA1-mediated membrane fusion. Journal of Biological Chemistry (2024) DOI:10.1016/j.jbc.2024.108076
<概要>ミトコンドリアは二重の膜で構成されている特徴的なオルガネラで、主に細胞内で消費されるエネルギーの大半を産生する重要な場所です。このような活動を行うために、ミトコンドリアは絶えず融合と分裂によりその形態を維持していますが、その分子機構はこれまであまり理解されていませんでした。本研究では、ミトコンドリアの内膜に局在するタンパク質Prohibitin 1の働きを詳細に解析することで、ミトコンドリア内膜における融合機構の一端を再構成実験系により明らかにしました。本成果は、ミトコンドリア形態異常による疾患理解に大きな貢献が期待されます。ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:太田啓介)では、電子顕微鏡によるプロテオリポソームの解析支援を行いました。
お問い合わせ・ご相談はこちらまで
どの支援を受けたらよいかわからない。ABiSの支援対象になるかどうか申請前に確認したい。などはもちろんのこと、具体的な技術に関する質問など、バイオイメージングに関することならどんなことでもご相談ください。
バイオイメージング相談窓口ABiSに寄せられるよくある質問をQ&A形式でまとめました。申請される方はまずこちらをご参考ください。
よくあるご質問