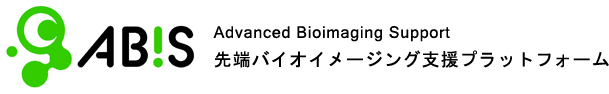成果発表
【電子顕微鏡支援:片岡洋祐(神戸大学)】[2025.12.24]
榎原智美 教授(明治国際医療大学)の論文が Nature Communications に掲載されました
ネズミのヒゲには制振装置が備わっていた
― 触覚情報を高精度に選別するメカニズムを解明 ―
<概要>本研究では、これまで解析が困難とされてきた単一細胞レベルの電気生理学的手法と3D電子顕微鏡解析法を組み合わせることで、種類の異なる触感覚受容器における機能と形態の同時観察を可能にしました。
その結果、ヒゲに分布する数百個の感覚受容器のうち約50個の棍棒状終末が、ヒゲを大きく動かして空振りしている際には全く反応せず、障害物に接触した場合にのみ選択的に反応することが明らかになりました。この棍棒状終末は、コラゲンに富む浮き輪状の塊の際に並んで埋もれており、この塊は振り子のように動く制振装置として機能している可能性が示されました。
ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:片岡洋祐)では、 array tomography 法による三次元構造解析を支援しました。
【光学顕微鏡支援:藤森俊彦(基礎生物学研究所)】[2025.11.10]
西村浩平 講師(名古屋大学)の論文がCommunications Biology に掲載されました
<概要>本研究では、アフィニティリンカーを基盤とする改良型超高感度AID(AlissAID)システムを開発しました。これにより、培養動物細胞やマウス胚で、AIDタグを必要とする融合タンパク質に加え、タグなしのRasなどの標的タンパク質もオーキシン依存的に迅速に分解できるようになりました。さらに、光照射でタンパク質分解を精密に制御できるケージ化5-アダマンチルインドール-3-酢酸も開発し、内在性タンパク質の分解や局所的なタンパク質分解技術への応用が期待されます。ABiS・光学顕微鏡支援(支援担当:藤森俊彦)ではマウス初期胚におけるライブイメージングを支援しました。
【電子顕微鏡支援:渡辺雅彦(北海道大学)】[2025.06.20]
狩野方伸 教授(東京大学 現:帝京大学 特任教授)の論文がiScience に掲載されました
<概要>本研究ではプルキンエ細胞の転写因子ZFP64が、生後発達期に生じる登上線維シナプスの除去と樹状突起上への進展を促進することを明らかにしました。また、この過程にはP/Q型Ca²⁺チャネルおよびセマフォリン3A(Sema3A)の発現制御が関与することが示唆されました。ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:渡辺雅彦・山崎美和子)ではZFP64ノックダウン細胞での平行線維シナプスの微細構造と登上線維の支配様式に関する形態解析支援を行いました。
【MRI支援:青木茂樹(順天堂大学)】[2025.08.13]
中奥由里子 研究員(国立循環器病研究センター)の論文が Frontiers in Aging Neuroscience に掲載されました
<概要>
認知症の前段階とされる軽度認知障害(MCI)の早期発見は、認知症への進行予防のために重要です。本研究では、148名の地域在住高齢者の、年齢、性別、教育年数、認知機能検査スコアと脳MRI画像を用いて、MCIを検出するモデルを開発しました。マルチモーダルな脳MRI画像を含む多面的なマーカーを含めることにより、モデルの性能が有意に向上することを示しました。
ABiS・MRI支援(支援担当:青木茂樹、根本清貴)では、画像解析に関する指導を行いました。
【電子顕微鏡支援担当:小池正人(順天堂大学)】[2025.08.14]
平山尚志郎 助教(東京大学 現:浜松医科大学 特任講師)の論文が PLoS Biology に掲載されました
<概要>本研究では、加齢に伴いマウスやヒトの脳でヒアルロン酸プロテオグリカンリンクプロテイン2(HAPLN2)凝集体が増加することを、プロテオーム解析などにより明らかにしました。さらに、このHAPLN2凝集体が脳内のマイクログリアを活性化させ炎症を誘導すること、また酵素を用いて凝集体を除去するとマウスの運動機能が改善することも示しました。
ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:小池正人)では、HAPLN2のin vitro凝集体の電子顕微鏡観察を行い、その形状を評価する支援を行いました。
【光学顕微鏡支援担当:稲葉一男(筑波大学)】[2025.07.28]
上野裕則 教授(愛知教育大学)の論文が Cytoskeleton に掲載されました
<概要>原発性繊毛機能不全症(PCD)は、繊毛機能不全に関連する遺伝子変異によって引き起こされる先天性疾患です。
本研究では、PCDの原因遺伝子の一つであるDpcdを欠損させたノックアウトマウスを用いて、水頭症を呈したマウスの脳室上衣細胞の運動繊毛に運動異常が見られることを確認し、その原因として内腕ダイニンの部分的欠損が生じていることを明らかにしました。
ABiS・光学顕微鏡支援(支援担当・稲葉一男)では、位相差顕微鏡とハイスピードカメラを用い、脳室上衣繊毛の線毛運動を動画で撮影し、振幅、振動数、繊毛運動の曲率を測定する支援を行いました。
【画像解析支援:檜垣匠(熊本大学)】[2025.07.03]
高橋直紀 准教授(明治大学)の論文が Plant physiology に掲載されました
<概要>植物の根では、DNA損傷に応答して幹細胞が選択的に細胞死を起こし、その後に補充されることでゲノムの安定性が保たれる。本研究では、DNA損傷応答において中心的な役割を果たすSOG1転写因子が、オーキシンシグナルの抑制に働くIAA5とIAA29の発現を誘導し、オーキシンシグナルを低下させることで幹細胞の細胞死を促進する仕組みを明らかにした。
ABiS・画像解析支援(支援担当・檜垣匠)では、画像解析ソフトを使用し、植物の組織構造の数値化の支援を行いました。
【電子顕微鏡支援:山崎美和子(北海道大学)】[2025.07.03]
岡崎朋彦 准教授(北海道大学)の論文が Science に掲載されました
GGCX膜トポロジー反転による細胞質タンパク質カルボキシル修飾の発見
~ビタミンKが抗ウイルス防御に働く新たな仕組みを同定~
<概要>抗ウイルス応答を担うMAVSが、ビタミンK依存酵素GGCXによって細胞内で修飾される新たな仕組みを解明しました。GGCXの膜トポロジー反転により、細胞の防御戦略を切り替える“分子スイッチ”が働くことが明らかになりました。
ABiS・電子顕微鏡支援(支援担当:山崎美和子)では、GGCX発現細胞の切片作製およびC末端の電子顕微鏡観察に関する支援を行いました。
【MRI支援担当:林拓哉(理化学研究所)】[2025.06.19]
松平泉 助教(東北大学)の論文が iScience に掲載されました
脳の「かたち」は父に似るのか母に似るのか? 親子の脳が類似する性別ごとのパターンを発見
<概要>本研究では、父・母・子からなる「親子トリオ」の脳MRI画像を用いて、子の脳のどの部分が、父親と母親のどちらに似ているのかを詳細に調べました。その結果、子の脳には「父親にのみ似る部分」「母親にのみ似る部分」「両親に似る部分」「どちらにも似ない部分」が存在することを発見しました。ABiS・MRI支援(支援担当・林拓也)では、Human Connectome Project Multi-Modal Parcellation version 1.0に基づいて皮質厚や表面積などを算出する支援を行いました。
 プレスリリース(東北大学のサイト)
プレスリリース(東北大学のサイト)
 プレスリリース(加齢医学研究所のサイト)
プレスリリース(加齢医学研究所のサイト)
 プレスリリース(学際高等研究教育院のサイト)
プレスリリース(学際高等研究教育院のサイト)
 プレスリリース(学際科学フロンティア研究所)
プレスリリース(学際科学フロンティア研究所)
【光学顕微鏡支援担当:今村健志(愛媛大学)】[2025.03.26]
宿南知佐 教授(広島大学)の論文が Development に掲載されました
“光る”遺伝子改変マウスで探る腱・靱帯が筋骨格をつなぐしくみの解明 〜体を動かす組織の成り立ちを立体的に“見える化”し、疾患研究の新たな糸口に〜
<概要>本研究では、ScxTomato;Sox9EGFPレポーターマウスを用いて腱・靱帯と軟骨の組織間相互作用を調べることにより、Scxが腱・靱帯の成熟のみならず、筋肉の形成や骨への付着も制御していることを発見しました。ABiS・光学顕微鏡支援(支援担当:今村健志)では、共焦点および二光子励起顕微鏡を使用し、胚組織の高解像度三次元イメージング解析を支援しました。
 プレスリリース(広島大学のサイト)
プレスリリース(広島大学のサイト)
 プレスリリース(広島大学(英語版)のサイト)
プレスリリース(広島大学(英語版)のサイト)
 プレスリリース(Asia Research Newsのサイト)
プレスリリース(Asia Research Newsのサイト)
お問い合わせ・ご相談はこちらまで
どの支援を受けたらよいかわからない。ABiSの支援対象になるかどうか申請前に確認したい。などはもちろんのこと、具体的な技術に関する質問など、バイオイメージングに関することならどんなことでもご相談ください。
バイオイメージング相談窓口ABiSに寄せられるよくある質問をQ&A形式でまとめました。申請される方はまずこちらをご参考ください。
よくあるご質問