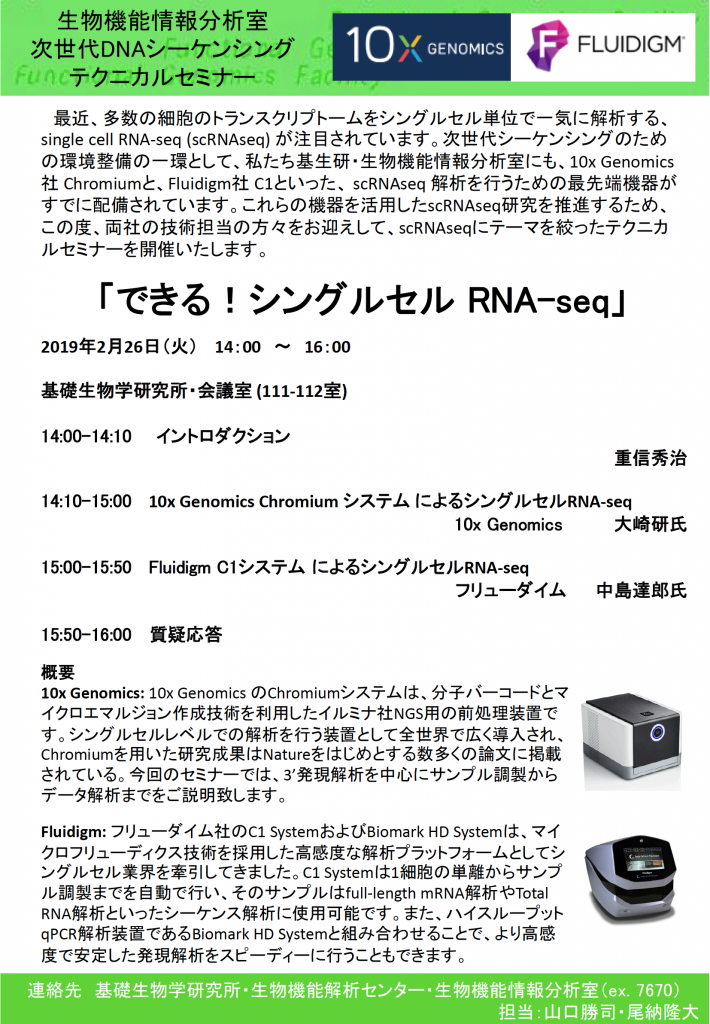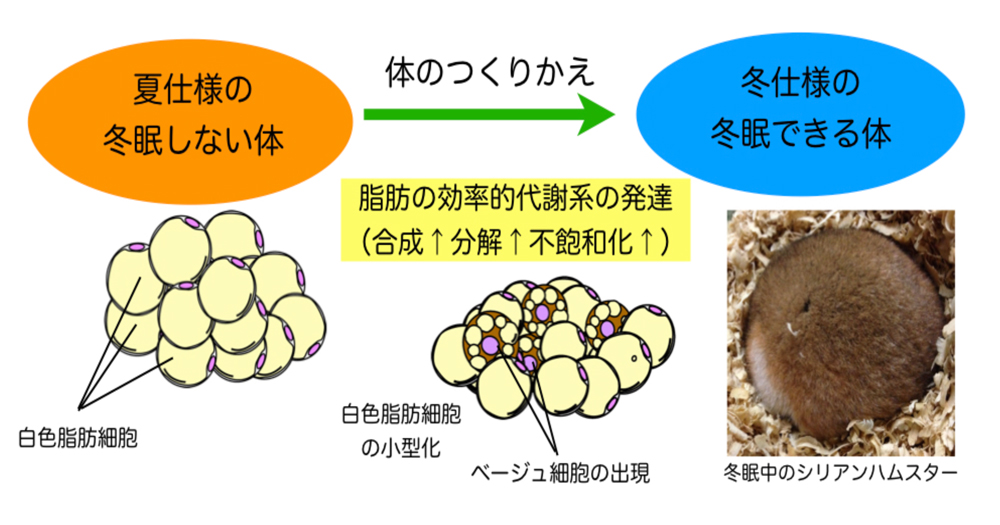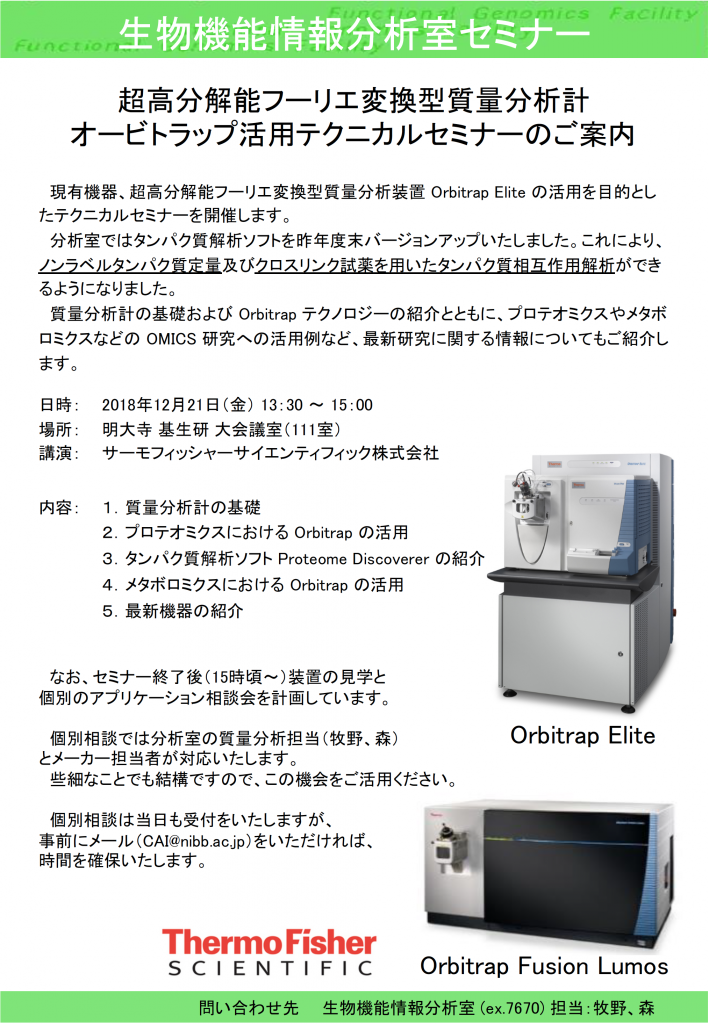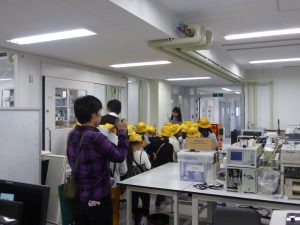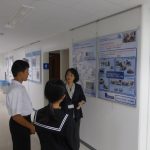皆様
最近、多数の細胞のトランスクリプトームをシングルセル単位で一気に解析する、
single cell RNA-seq (scRNAseq) が注目されています。次世代シーケンシングのた
めの環境整備の一環として、私たち基生研・生物機能情報分析室にも、10x Genomics 社 Chromium と、Fluidigm 社 C1 といった、 scRNAseq 解析を行うための最先端機器が
すでに配備されています。これらの機器を活用した scRNAseq 研究を推進するため、この度、両社の技術担当の方々をお迎えして、scRNAseq にテーマを絞ったテクニカルセミナーを開催いたします。
「できる!シングルセル RNA-seq」
日時:2019 年 2 月 26 日(火)14:00 ~ 16:00
場所:基礎生物学研究所・会議室 ( 111 – 112 室)
プログラム:
14:00 – 14:10 イントロダクション
重信秀治
14:10 – 15:00 10x Genomics Chromium システム によるシングルセル RNA-seq
10x Genomics 大崎研氏
15:00 – 15:50 Fluidigm C1 システム によるシングルセル RNA-seq
フリューダイム 中島達郎氏
15:50 – 16:00 質疑応答
連絡先:
基礎生物学研究所・生物機能解析センター・生物機能情報分析室
担当:山口勝司・尾納隆大( ex. 7670 )