イモリの再生能力の謎に迫る遺伝子カタログの作成
~新規の器官再生研究モデル生物イベリアトゲイモリ~
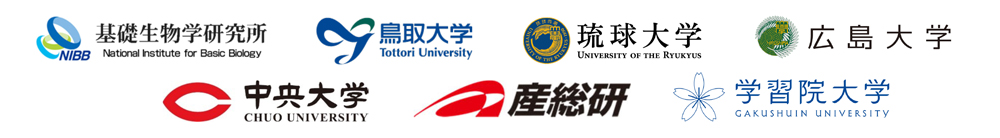
中央大学・産業技術総合研究所・学習院大学
【本研究成果のポイント】
- 新規モデル生物イベリアトゲイモリの遺伝子カタログを作成した。
- 遺伝子カタログをはじめとする様々なイベリアトゲイモリ研究情報を世界中の研究者が利用できるようにするためのポータルサイト“iNewt”(http://www.nibb.ac.jp/imori/main/)を開設した。
- 本研究の成果は、イモリの高い器官再生能力の解明をはじめとする様々な研究に不可欠なツールやヒントとなり、今後の再生医療研究を含む多様な分野への貢献が期待される。
【研究の概要】
両生類のイモリは、非常に高い再生能力を持っていることで知られ、再生医学や発生生物学における重要な実験動物として1世紀以上の研究の歴史を持っています。なかでも、繁殖や飼育が簡便なイベリアトゲイモリ(Pleurodeles waltl)は新しいモデル生物として脚光を浴びています。実験室での飼育や繁殖が容易なイベリアトゲイモリの有用性に着目した日本人の研究者でコンソーシアムを作り、飼育システムの確立、近交系の確立、高効率のゲノム編集法の開発など研究基盤の構築を推進してきました。現在では、イベリアトゲイモリは画期的な新興モデル生物として世界中の研究者から注目を浴びており、研究者人口が急速に増えています。しかし、イベリアトゲイモリには、ゲノムが巨大などの理由で研究の基盤となる遺伝子の情報がほとんど整備されていないという問題がありました。今回、基礎生物学研究所の重信秀治教授ら、鳥取大学医学部の林利憲准教授(現 広島大学教授)ら、琉球大学大学院医学研究科の松波雅俊助教ら、ほか広島大学、中央大学、産業技術総合研究所、九州大学、学習院大学の研究者から構成される研究チームは、イベリアトゲイモリの網羅的遺伝子カタログ作成に成功しました。各研究室から持ち寄った29種類もの多様なイベリアトゲイモリ試料からRNAを抽出し、次世代シーケンシング技術によるRNA-seq法により遺伝情報を解読しました。得られた配列情報を大型計算機で解析することにより、202,788個のイベリアトゲイモリの遺伝子モデルを構築しました。これらのモデルを検証したところ、イベリアトゲイモリが保有する全遺伝子の約98%をカバーする網羅性の高い高品質の遺伝子カタログであることが確認されました。さらに、研究チームは、この遺伝子カタログを世界中の研究者と共有するためのポータルサイト“iNewt”(http://www.nibb.ac.jp/imori/main/)を開設しました。iNewtでは遺伝子カタログに加えて、ゲノム編集のプロトコルなどイベリアトゲイモリの研究リソース情報を無料で提供しています。本研究によって作成された遺伝子カタログを利用することで、ゲノム編集や、次世代シーケンサーを用いた遺伝子の発現解析など、イベリアトゲイモリを用いた研究が格段にスピードアップすることが期待されます。これにより、再生医療や発生生物学はもちろん、癌研究、幹細胞生物学、生殖生物学、進化学、毒性学などの研究分野でイモリを活用した研究が大きく発展することが期待されます。
本研究成果は、2019年4月22日に国際科学誌「DNA Research」に掲載されました。

【論文情報】
掲載誌:
国際科学誌 DNA Research
タイトル:
“A comprehensive reference transcriptome resource for the Iberian ribbed newt Pleurodeles waltl, an emerging model for developmental and regeneration biology”
著者名:
Masatoshi Matsunami1, Miyuki Suzuki2, Yoshikazu Haramoto3, Akimasa Fukui4, Takeshi Inoue5, Katsushi Yamaguchi6, Ikuo Uchiyama6, Kazuki Mori3, Kosuke Tashiro7, Yuzuru Ito3, Takashi Takeuchi8, Ken-ichi T Suzuki2, 6, Kiyokazu Agata5, Shuji Shigenobu6*, and Toshinori Hayashi8*
所属: 1. 琉球大学大学院医学研究科、2. 広島大学大学院理学研究科、3. 産業技術総合研究所、4. 中央大学理工学部生命科学科、5. 学習院大学理学部生命科学科、6. 基礎生物学研究所、7. 九州大学大学院、8.鳥取大学医学部生命科学科、*: 責任著者
DOI:
10.1093/dnares/dsz003 (https://doi.org/10.1093/dnares/dsz003)
詳しくは以下のページをご覧ください。
http://www.nibb.ac.jp/press/2019/04/24.html

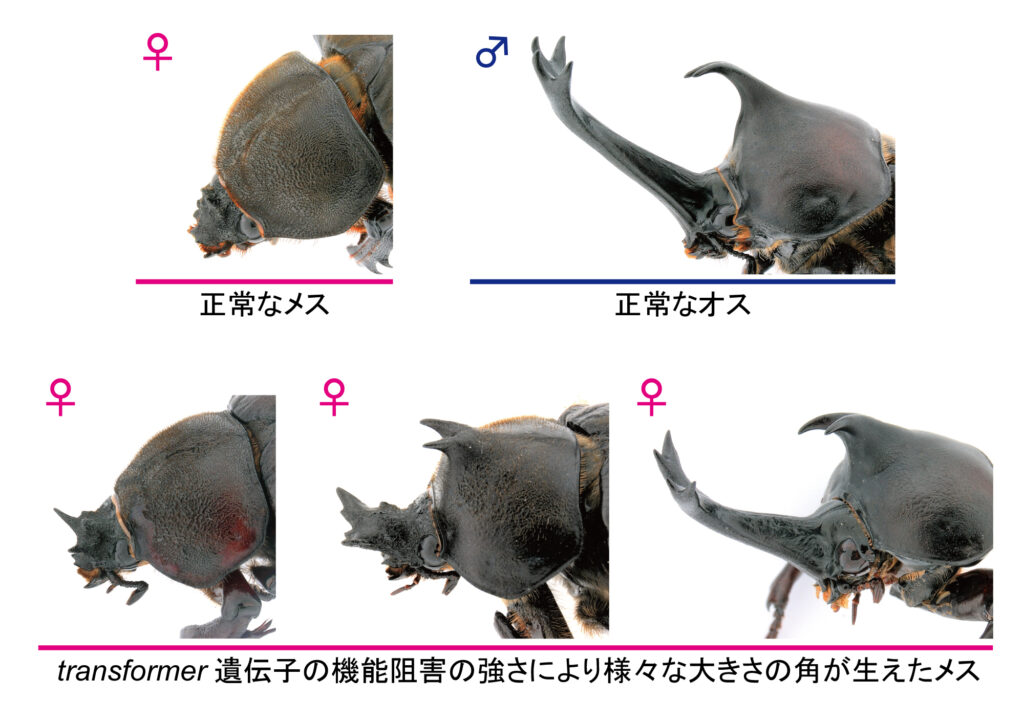
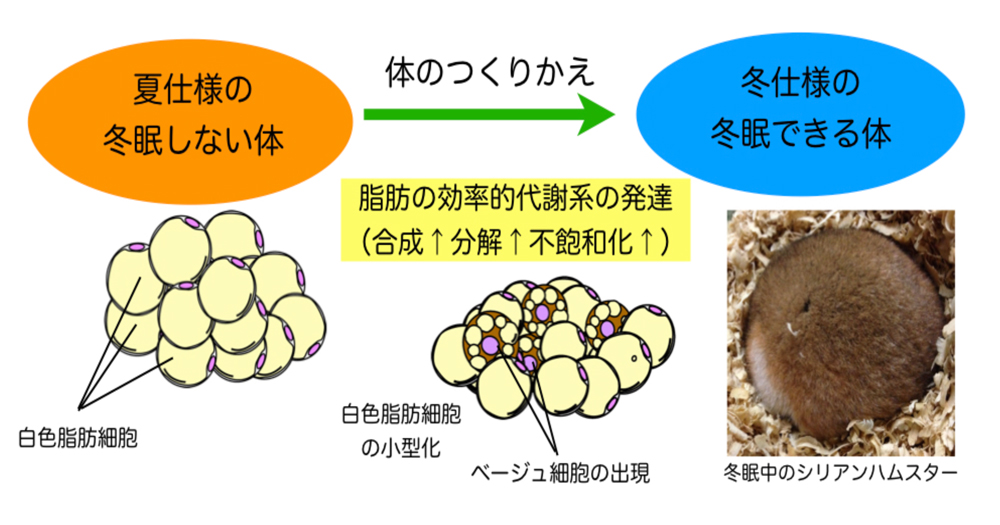

 図:ナミテントウの多様な翅の斑紋
図:ナミテントウの多様な翅の斑紋