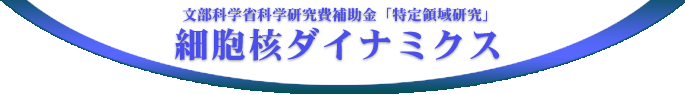| |
| 研究内容 |
染色体は細胞が分裂する際、複製されたゲノムDNAを2つの娘細胞に正確に分配するために必須な構造体である。それでは、分裂期染色体はどのようにして1本の長いDNAから折り畳まれているのだろうか。この問題は長年に渡って生物学者たちの興味を集めてきた。直径2nmのDNAはまずヒストンに巻かれてクロマチンになるが、これがどのように折り畳まれて直径約1μmの染色体になるのか、その高次構造は未だ明らかではない。
私たちは染色体の高次構造理解を目的として研究を進め、「染色体scaffold」と呼ばれる、染色体からヒストンを除いた分画が、主にtopoisomerase IIa(トポIIa)とコンデンシンから構成されていることを示した。そして、そのいずれもが染色体に軸状に存在することを明らかにした。
それではこれらの分子はどのようにしてクロマチンを折り畳んでいるのだろうか。この問いに答えるために、前述のように透過電子顕微鏡などを用いて、染色体中のクロマチンを実際に「見る」ことは必須である。しかしながら、通常の透過電顕はもとのイメージのprojectionを見ているため空間的な情報は得られない。そこで、私たちは透過電子顕微鏡tomography(断層撮影法)を用いて染色体の3次元再構築をおこなっている。これまでの実験により、1本1本のクロマチン繊維のイメージングに成功し、染色体中のクロマチン繊維を辿っていくことが可能となった。また、染色体軸がどのようにクロマチン繊維をorganizeするのかを明らかにするために、染色体軸と結合するヒトゲノム上のDNAエレメントをDNAチップを用いて体系的にマッピングしている。以上のように、染色体のクロマチン繊維を「見て」、そして染色体軸に結合するDNAエレメントを「知る」ことにより、「どのようにして染色体が1本の長いクロマチン繊維から折り畳まれているのか?」を理解し、染色体のクロマチンorganizationに隠されたヒトゲノムの高次の情報を明らかにしていく予定である。
さらに、ゲノムの理解のためには、ゲノムが納められている細胞核という「入れ物」の構造とその構築原理を知ることが必要不可欠である。このため、最近、核膜上のもっとも顕著な構造体である核膜孔を指標として、細胞核の動的な形成過程の解析を開始した。その結果、核膜上の核膜孔の分布には大きな偏りがあることが明らかになった。そして、核膜孔の数や分布は細胞核が変化する細胞周期や分化の過程でダイナミックに変化することを示した。これらの観察に基づき、現在、核膜孔の 形成過程及び細胞核膜の構築過程を種々のイメージング技術をもちいて追求している。ゲノムの高次構造は、核膜が崩壊し、ゲノムが「むき出し」になっている分裂期染色体においても何らかの形で保持されている。このため、前述の分裂期染色体の構造解析で得られる知見は細胞核研究においても極めて重要である。今後、これらの研究から得られた知見を踏まえて、「細胞核においてその中に包含されるゲノムDNAがどのように折り畳まれ、どのように配置されるか」を明らかにし、細胞核が遺伝子発現などのヒトゲノム機能を支える基盤としてどのように機能しているかを解明していきたい。 |
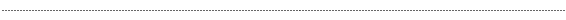 |
前島 一博(研究代表者)
<理化学研究所・今本細胞核機能研究室・基礎科学特別研究員> |