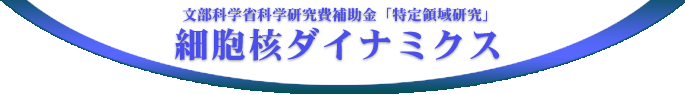Tatsuo Fukagawa, Masahiro Nogami, Mitsuko Yoshikawa, Masashi Ikeno, Tuneko Okazaki, Yasunari Takami, Tatsuo Nakayama, and Mituso Oshimura "Dicer is essential for formetion of the heterochromatin structure in vertebrate cells." Nature Cell Biology (2004) Vol. 6, 784-791. & Cover.
Tetsuya Hori, Tokuko Haraguchi, Yasushi Hiraoka, Hiroshi Kimura, and Tatsuo Fukagawa "Dynamic behavior of Nuf2-Hec1 complex that localizes to the centrosome and centromere and is essential for mitotic progression in vertebrate cells." Journal of Cell Science (2003) Vol. 116, 3347-3362.
Ai Nishihashi, Tokuko Haraguchi, Yasushi Hiraoka, Toshimichi Ikemura, Vinciane Regnier, Helen Dodson, William C. Earnshaw, and Tatsuo Fukagawa "CENP-I is essential for centromere function in vertebrate cells." Developmental Cell (2002) Vol. 2, 463-476.
Tatsuo Fukagawa, Yoshikazu Mikami, Ai Nishihashi, Vinciane Regnier, Tokuko Haraguchi, Yasushi Hiraoka, Naoko Sugata, Kazuo Todokoro, William Brown, and Toshimichi Ikemura "CENP-H, a constitutive centromere component, is required for centromere targeting of CENP-C in vertebrate cells." The EMBO Journal (2001) Vol. 20, 4603-4617. |