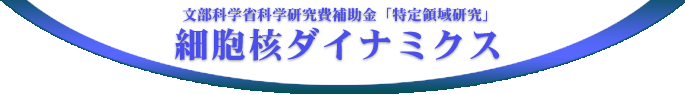Hosoya, O., Tsutsui, K. and Tsutsui, K. Localized expression of amphiphysin Ir, a retina-specific variant of amphiphysin I, in the ribbon synapse and its functional implication. Eur. J. Neurosci., 19: 2179-2187 (2004)
Purbowasito, W., Suda, C., Yokomine, T., Zubair, M., Sado, T., Tsutsui, K. and Sasaki, H. Large-scale identification and mapping of nuclear matrix-attachment regions in the distal imprinted domain of mouse chromosome 7. DNA Research, 11: 391-407 (2004)
Yamada, M., Hayashi, K., Hayashi, H., Ikeda, S., Hoshino, T., Tsutsui, K., Tsutsui, K., Iinuma, M. and Nozaki, H. Stilbenoids of Kobresia nepalensis (Cyperaceae) exhibiting DNA topoisomerase II inhibition. Phytochemistry, 67: 307-313 (2006)
Bode, J., Winkelmann, S., Gotze, S., Spiker, S., Tsutsui, K., Bi, C., Prashanth, A. K. and Benham, C. Correlations between scaffold/matrix attachment region (S/MAR) binding activity and DNA duplex destabilization energy. J. Mol. Biol. , 358: 597-613 (2006)
Lobov, I.B., Tsutsui, K., Mitchell, A.R., and Podgornaya, O.I.: Specific interaction of mouse major satellite with MAR-binding protein SAF-A. Eur. J. Cell Biol., 79, 839-849, 2000
Tsutsui, K., Tsutsui, K., Hosoya, O., Sano, K., and Tokunaga, A.: Immuno-histochemical analyses of DNA topoisomerase II isoforms in developing rat cerebellum. J. Comp. Neurol.,431, 228-239, 2001
Tsutsui, K., Tsutsui, K., Sano, K., Kikuchi, A., and Tokunaga, A.: Involvement of DNA topoisomerase IIb in neuronal differentiation. J. Biol. Chem., 276, 5769-5778, 2001
Tohge, H., Tsutsui, K., Sano, K., Isik, S., and Tsutsui, K.: High incidence of antinuclear antibodies that recognize the matrix attachment region. Biochem. Biophys. Res. Commun.,285, 64-69, 2001
Lobov, I.B., Tsutsui, K., Mitchell, A.R., and Podgornaya, O.I.: Specificity of SAF-A and lamin B binding in vitro correlates with the satellite DNA bending state. J. Cell. Biochem., 83, 218-229, 2001
Shimizu, N., Miura, Y., Sakamoto, Y., and Tsutsui, K.: Plasmids with a mammalian replication origin and a matrix attachment region initiate the event similar to gene amplification. Cancer Res., 61, 6987-6990, 2001
Watanabe, M., Tsutsui, K., Hosoya, O., Tsutsui,K., Kumon, H., and Tokunaga, A.: Expression of amphiphysin I in Sertoli cells and its implication in spermatogenesis. Biochem. Biophys. Res. Commun., 287, 739-745, 2001
Terada, Y., Tsutsui, K., Sano, K., Hosoya, O., Ohtsuki, H., Tokunaga, A., and Tsutsui, K.: Novel splice variants of amphiphysin I are expressed in retina. FEBS Lett., 519, 185-190, 2002
Isik, S., Sano, K., Tsutusi, K., Seki, M., Enomoto, T.,Saitoh, S., and Tsutsui, K.: The SUMO pathway is required for selective degradation of DNA topoisomerase II beta induced by a catalytic inhibitor ICRF-193. FEBS Lett.546, 374-378, 2003
Tomizawa, K., Sunada, S., Lu, Y., Oda, Y., Kinuta, M., Ohshima, T., Saito, T., Wei, F., Matsushita, M., Li, S., Tsutsui, K., Hisanaga, S., Mikoshiba, K., Takei, K., and Matsui, H.: Cophosphorylation of amphiphysin I and dynamin I by Cdk5 regulates clathrin-mediated endocytosis of synaptic vesicles. J. Cell Biol.163, 813-824, 2003
Hosoya, O., Tsutsui, K., and Tsutsui, K.:Localized expression of amphiphysin Ir, a retina-specific variant of amphiphysin I, in the ribbon synapse and its functional implication. Eur. J. Neurosci., 19, 2179-2187, 2004
Purbowasito, W., Suda, C., Yokomine, T., Zubair, M., Sado, T., Tsutsui, K., and Sasaki, H.: Large-scale identification and mapping of nuclear matrix-attachment regions in the distal imprinted domain of mouse chromosome 7. DNA Research (in press) |